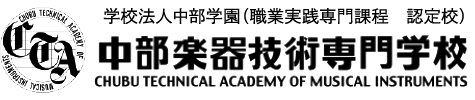2025年7月8日(火)、作曲家・天野正道先生をお招きし、管楽器リペア科1年生の授業「吹奏楽総合研究」が行われました!
今回は、「演奏する」「聴く」「分析する」すべての視点から音楽を深める、特別な授業です。その一部を、高校生のみなさんにもわかりやすくご紹介します♪

① チューニングって“音を合わせるだけ”じゃない!
天野先生の第一声は…
「チューナーで合わせるのは“最低限”。大事なのは、仲間の音を聴いて合わせること。」
合奏の中では、グループごとにピッチ(音の高さ)を揃え、全体でバランスを取っていくのがポイント。生徒たちは真剣な表情で、仲間の音に耳を澄ませていました。
② 音を出す前に“イメージ”が命!
「何の音を出したいか、頭の中でしっかり描いてから吹こう。」
木管楽器は実際に声に出して、金管楽器は“歌口”を使ってイメージを確認。音をただ出すのではなく、「こんな音を出したい!」という気持ちが音に表れて、演奏に立体感が生まれます。もちろん打楽器も同じ!全員が“イメージ”の大切さを実感しました。
③ 耳を鍛えることが、上達のカギ!
「音楽の基礎は“耳”!聴く力を育てることが、演奏にもリペアにもつながる。」
ソルフェージュ(音感トレーニング)は、ただの練習ではなく、将来リペア技術者として活躍するためにも大切。耳を使って音を感じ取る力が、楽器の状態を判断する力にもなっていくんですね!
④ 課題曲を“深掘り”分析!増4度は悪魔の音?
課題曲を分析(アナリーゼ)する中で、天野先生からこんな一言。
「“増4度”は“悪魔の音程”って呼ばれてるけど、だからこそしっかり吹き込んで表現しよう。」
楽譜に書かれた記号だけでなく、そこに込められたサウンドカラーや作曲家の意図を読み取ることが大切。楽譜の奥にある“音楽”を見つける面白さを、みんなで体感しました。
⑤ 音楽は“1枚の絵”として感じる!
2コマにわたる授業の最後は、課題曲を通しての演奏!
「曲全体を理解すると、音楽がまるで1枚の絵のように感じられる。」
天野先生の指揮のもと、全員が気持ちを一つにし、1つの作品を“創り上げる”感覚を体験しました。



◎まとめ:音を出す前に、まず“感じること”!
今回の授業では、「ただ音を出す」のではなく、
聴く力(耳)
イメージする力(想像力)
が、音楽をつくるうえでどれだけ大切かを改めて学びました。