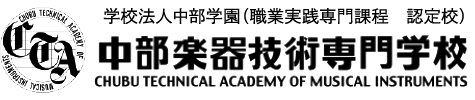こんにちは!管楽器リペア科1年生です。長かった暑さもようやく落ち着いて、季節はすっかり秋になりました。
私たち学生は8月下旬に夏休みが終わり、前期末試験を受けました。試験は、修理の内容や楽器の構成論など、全部で5科目。幅広い知識を問われるのですが、私が一番苦戦したのは「楽典」でした。
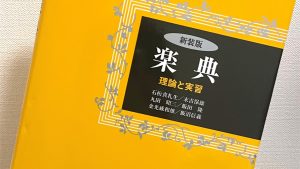
楽典とは、音楽のルールを学ぶ授業で、いわば“音楽の文法”。「修理に関係あるの?」と思うかもしれませんが、実はとても大切なんです。
たとえば、同じ楽譜の音でも楽器によって響き方が違ったり、キィの名前に音名が使われていたり…。
楽典を理解していないと、楽器のことを深く理解するのが難しくなってしまいます。
授業では、これまで楽典を習ったことがある人もいれば、初めて学ぶ人もいました。そこで、グループワークを通してお互いに教え合ったり、自分の言葉で説明したりして、みんなで協力しながら勉強しました。
吹奏楽部出身の人も多いのですが、担当していた楽器と違う譜表に戸惑うこともあり、試験勉強はなかなか大変。でも、楽典がわかるようになると音楽の見え方が変わり、今まで演奏してきた曲がもっと面白く感じられるんです!
楽典のテキストは、書店や楽器店で気軽に手に入れることができます。
音楽や楽器が好きな人ならきっと楽しめると思うので、ぜひ一度触れてみてください!