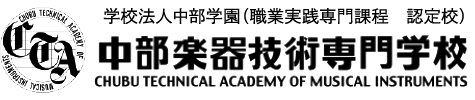こんにちは!管楽器リペア科2年生です!今回は、授業で取り組んでいる「サックスの修理」についてご紹介します。
私たちが行っている主な作業は、タンポの交換、バランス調整、そして試奏(実際に吹いてみること)です。まず、「タンポ」と「バランス」って何?という人のために簡単に説明しますね!
◎タンポってなに?
タンポは、サックスのキー(押さえる部分)の裏についている丸いパッドのこと。サックスには「トーンホール」という音を出すための穴がたくさんあり、このタンポがキーを押したときにしっかりと穴をふさいで、空気が漏れないようにしてくれます。

◎バランス調整とは?
木管楽器は、一つのキーを押すと他のキーも連動して動く仕組みになっています。「バランス調整」とは、すべての音がちゃんと出るように、キーがぴったり閉じるようにする作業です。2つのキーが同時に閉じる必要があるので、かなり繊細な調整が求められます。
◎1年生と2年生の違い
1年生のときは、タンポを交換してバランスを取ったら、そこで作業は終了でした。でも2年生になると、「試奏して音がちゃんと鳴るか」をチェックするようになります。これが意外と難しいんです……!
私は普段サックスを吹かないので、楽器の調子が悪いのか、自分の吹き方が悪いのか、分からなくなることがあります。
例えば「ド」の音を吹いても、うまく鳴らない。「これ、私のせい?それとも楽器?」と迷ってしまうことも…。
そんなときは、一度立ち止まって確認します。
・タンポの位置はあってる?
・バランスはズレてない?
見直してみると、小さな隙間が空いていたり、キーがちゃんと閉じていなかったり、意外な原因が見つかることがあります。
再調整をしてから試奏してみると……
さっきまで出なかった音が鳴った瞬間、「やった!」という達成感があるんです!
◎最後に
このサックス修理の実習を通して、私は「確認の大切さ」と「焦らず1つ前に戻る勇気」を学びました。うまくいかない時も、諦めずに原因を探っていけば、ちゃんと音が鳴る楽器に仕上がります。
「音が出る」って、当たり前じゃない。手をかけて、工夫して、やっと出せる音なんだと感じました。